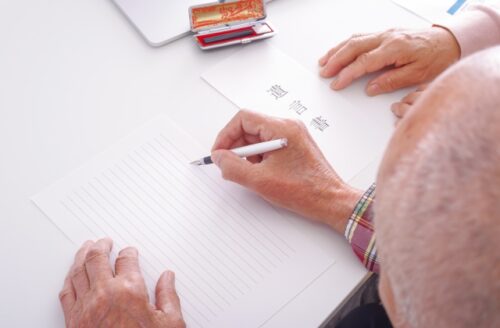農福連携を広めていきたい!
皆様は、ノウフクの日が11月29日であることはご存知でしょうか。
農福連携とは、農業と福祉の連携、簡潔に言うと、農業従事者と福祉の対象とする方との連携です。
農業側の課題としては、農業者の高齢化に伴う農業者数や耕地面積の減少があり、一方福祉側の課題としては、障害者の就労先の確保や工賃の引上げが進まないことがあげられます。
農業と福祉が連携することで 農業側のメリットとしては、農業経営体における労働力の確保や売上の増加があげられ、それが、規模拡大につなげ、また、社会貢献への寄与などがあげられます。福祉側のメリットとしては、福祉サービス事業所の賃金、工賃の向上や心身状況の改善が期待や、農業分野で活躍することを通じ、自信や生きがいを持って社会参画を実現していくことができます。また、障害者だけでなく、高齢者、生活困窮者、ひきこもり状態にある者、犯罪をした者など、取組の対象者は多岐に及びます。
2023年、2024年と行政書士として、農福連携の調査研究を行い、農福連携を進める行政や、実際に農福連携に取り組まれている、農家へのヒヤリングを行いました。自治体の中では、農業関係の課と、福祉関係の課が協力して進めており、農と福を有機的に繋げようとする職員の熱意を感じることができました。一方で、農福連携に関する補助金も、多くの自治体に存在するわけではなく、自治体次第であることも課題であることを感じました。
農家のヒヤリングですが、以前から福祉の力を活用することに意識の強かった方が、障害福祉サービス事業所と既に連携を取っており、農福連携を自然に進めている事業所も存在しておりました。ただ、1年じゅう仕事があるわけではないことと、草刈り機等の機械使用は安全上任せることは難しいので、コンスタントに仕事を受注し、安定した連携になるよう、一層の農福連携の認知や、仕事が安全に行える体制づくり等が課題であることにも改めて気づくことができました。また、農業者に、障害者等への対応方法や疾病について等、連携するうえで必要な情報や知識を学ぶ場があると良いのではないかと考えました。
毎年各地で様々な、農福連携に関する、イベントや講座があり、自治体での独自の補助金制度等、ソフト面、ハード面でのサポートも存在します。農業を就労として、生きがいとして取り入れたいサービス事業所があったとしても、どこに農地があり、事業所として運営していくのが良いのか、それとも請負で農業に関わることが良いのか等、選択に迷うことがあるかもしれません。その中で、従事する場所の環境を確認することは、とても大切なことです。
農地や周辺環境を確認するために、eMAFF農地ナビ(https://map.maff.go.jp/?dlgName=jusho)や地域の農業委員会へ相談することをお勧めします。また、農作業の指導をお願いしたい場合は、近隣の農業経験者への依頼や、都道府県の普及指導センター等に相談することをお勧めします。農福連携のための農園整備や体験施設の整備支援のために、国や都道府県単位でも補助金がありますので、うまく活用できれば良いですね!!
最後までご覧いただき、ありがとうございました!!